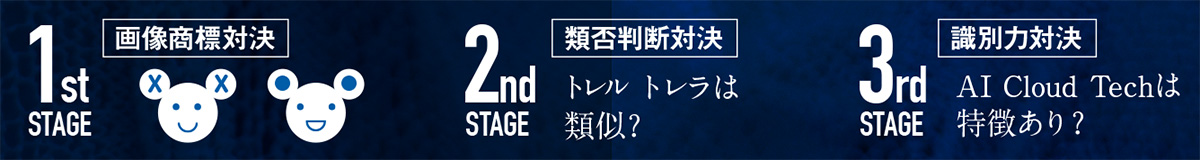10/28(月)、29(火)、30(水)の3日間、IPBC Asiaが、東京丸の内のパレスホテルで開催されます。
パレスホテルというと、先日トランプ大統領が宿泊したホテルです。
モビリティの将来、人間対機械、特許プラスアルファ、5G-未来の幕開けなど、興味深い内容もあります。
参加費が1950ドルと高く、2日以上実務ができなくなるため、自分は参加見送りの方向です。
時間が取れる方は、海外人材と交流もでき、良いのではないでしょうか。
http://events.ipbc.com/events/ipbc-asia-2019/agenda-0aabbc896b004d0ebc1c33eed6077508.aspx
月曜日, 10 28, 2019
15:30 - 18:30
登録
17:30 - 19:30
オープニング レセプション
火曜日, 10 29, 2019
08:15 - 09:15
受付・朝食
09:15 - 09:45
来賓挨拶
09:45 - 11:00
世界を覆う不確実性への対応
アジアの有力知財企業のトップが、より不透明感を増す技術・政治的環境をどう乗り越えていくかについて議論する。
• 貿易と技術を巡る緊張関係
• 注目すべき反トラストの動向
• インダストリー 4.0 - 特許の衰退か?
Speakers:
グスタフ・ ブリスマーク, Min-Sheo Choi, Kimberly Chotkowski, 比嘉 正人, 童 心
Moderator:
ジョセフ・ シーノ
11:00 - 11:30
ネットワーキング ブレイク(休憩)
11:30 - 12:45
ディール・メーキングの新局面
新たな産業のダイナミクス、政策転換ならびに革新的な技術が、知財の取引に対する従来のアプローチに大きく影響している。新たなディール・ストラクチャーがどのように交渉の全当事者に好結果をもたらし得るかについて、世界をリードする知財ストラテジストが見解を語る。
•シンジケート・ディールの利点
•異業種間の合意形成
•全員が勝利する道
Speakers:
カート・ ブラッシュ, 藤木 実, 長澤 健一, Stefan Tamme, ジュディー・ イー
Moderator:
ギルバート・ ウー
12:45 - 14:30
昼食
14:30 - 15:45
午後の分科会
14:30 - 15:45
知財 = マネー
投資家が知財市場への資本投入を再開している。かつて金融業界主導による同分野への進出は、好結果ばかりではなかったが、今回こそは違う結果になるかもしれない。
•誰がなぜ知財に投資するか
•投資は特許市場のどこに向かうか
•特許資産はM&Aにどう組み込まれるか
Speakers:
Elvir Causevic, ジョセフ ・ケスラー, ジェイソン・ ロー, 中村 達生, 朴 昌海
Moderator:
Kent Richardson 任意
14:30 - 15:45
アジアの成長市場における成功
高度な製造技術とR&D活動のホットスポットになりつつあるASEANや東南アジアのダイナミックな経済活動の中で、豊かな知財資産を有する組織はますます多くの機会を捉えている。
•南へ拠点を移す製造活動
•現地R&Dの最大活用
•権利行使の現状
Speakers:
金野 諭, Bernard Lau, 吉田 伸 任意
14:30 - 15:45
モビリティの将来
知財は自動車産業で起きている革命の中心をなしている。サプライチェーンの新規参入者と破壊的なビジネスモデルが産業のランドスケープを一変させるなか、リスク管理と価値創造がこれまでになく重要となる。
•提携の原動力としての特許の役割
• 統合によって生じる危険性
• 新たな市場プレーヤーとその重要性
Speakers:
Mitsuru Araki, Raymond Chen, 大島 裕史, Matteo Sabattini
Moderator:
ヘンリック・ オルソン 任意
15:45 - 16:15
ネットワーキング ブレイク(休憩)
16:15 - 17:30
午後の分科会
16:15 - 17:30
人間対機械
知財管理の将来はどちらに委ねられるか。知財担当の経営幹部が、AI主導型分析ツールと優秀な知財専門家の双方を最大限活用する方法について議論する。
•スピードと品質のバランス
•企業の知財費用の管理
•自動化 - どこまでが行き過ぎか?
Speakers:
周 延鵬, ヴィジャヤ・クマル・ カデルバッド, Santosh Metri, スコット・ シュナイダー 任意
16:15 - 17:30
生命科学の新ダイナミクス
アジア太平洋地域は製薬業界の研究の一大拠点となりつつあるものの、開発レベルは国・地域により大きく異なる。
•ビッグデータと個別化医療 - 知財の影響
•バイオテク・イノベーションの強化
•知財戦略を方向付ける規制の最新動向
Speakers:
Alvin Deng, アルシャド・ ジャミル 任意
16:15 - 17:30
特許プラスアルファ
技術をめぐるランドスケープの大変化に伴い特許の適格性を巡る問題がさらに拡大している。知財に対する狭い見方を打破して、発明とイノベーションの保護に向けた総合的アプローチの道を切り開くことが必要不可欠となる。
•包括的知財戦略の策案
•営業秘密文化の構築
•ソフトウェア保護への新アプローチ
Speakers:
Vikran Duangmanee, ジリ・ ラシー, 吉田 直樹, パトリック・ ジャン, 周 国军 任意
17:30 - 19:00
カクテルレセプション
19:00 - 22:00
アジア知財エリートガラディナー(別途チケット購入)
水曜日, 10 30, 2019
08:30 - 09:30
朝食
09:30 - 09:45
Keynote address
Keynote Speaker:
松永 明
09:45 - 11:00
5G - 未来の幕開け
今年は、アジア全域で5G製品が新発売される節目の年となる。この世代のワイヤレス技術がどのような形で業界の再編や知財ビジネスの変革をもたらすかについて、標準化や実施プロセスの各分野のステークホルダーが議論する。
•ライセンス供与のランドスケープの概観
•ロイヤルティ料率の最初の値付け
•コネクテッド・エコノミー
Speakers:
安藤 禎宣, Mattia Fogliacco, Mathias Hellman, スザンナ・ マルティカイネン, Shizuka Sayama
Moderator:
マイク・ マクリーン
11:00 - 11:30
ネットワーキング ブレイク(休憩)
11:30 - 12:45
中国版チェックリスト
中国市場は独特で複雑だが外国の知財権者でも成功することはできる。重要なのは、自身のビジネス上の必要性だけでなく、現地の実状に合わせた戦略を構築することである。
•新たな知財控訴裁判所の影響
•パートナーシップおよび協力関係における知財保護
•ビジネスリスクの軽減
Speakers:
Jianguang Du, Greg Kisor, Bin Sun, 赵 杰
Moderator:
Jun Qiu
12:45 - 14:30
昼食
14:30 - 15:45
午後の分科会
14:30 - 15:45
データの威力
構造化された情報が巨大な価値の源泉であることを企業が理解し始めている。データの威力を発揮させるには知財部門の役割が不可欠である。
•有用なデータの特定
•最善の保護戦略
•価値創造の機会
Speakers:
ローレンス・ デイビス, Steven Liu, 田中 伸生 任意
14:30 - 15:45
日本の特許の優先性
第4次産業革命下で生き抜くための日本企業の変革に向けて知財ができることについて、有力技術系企業の幹部が見解を語る。
•常に時代を先取り
•リスクと機会の見極め
•政策改革の優先順位
Speakers:
川名 弘志, 大水 眞己
Moderator:
ウィル ・ジャスプリザ 任意
15:45 - 16:15
ネットワーキング ブレイク(休憩)
16:15 - 17:30
午後の分科会
16:15 - 17:30
紛争の動向
テクノロジー・コンバージェンスおよびライセンス交渉でさえも紛争の要因となり得る。その結果通常は訴訟となるが必ずしもその手段をとる必要はない。新たな紛争の解決方法が広がりつつある。
・訴訟の現状を把握する
・裁判地の選び方 – その根拠
・代替の紛争解決方法を選ぶタイミング
Speakers:
Dongsuk Bae, エリック・ カーシュ
Moderator:
アレックス・ ウィルソン 任意
16:15 - 17:30
社内の知財部門の改革
Speakers:
ブレンダン・ チョン, リズ・ イーディー, 石島 尚, 片岡 将己, 若代 真吾
Moderator:
James Maccoun 任意
17:30 - 19:00
閉会のカクテルレセプション








![ビジネス法務 2019年 10 月号 [雑誌]](http://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ndIXnESjL._SL160_.jpg)